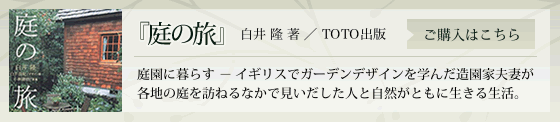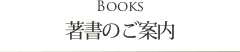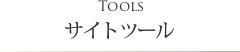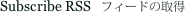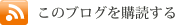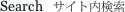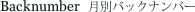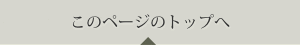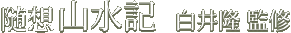第三巻 第一期湿原研究所ニュースレター・セレクション
一般社団法人湿原研究所は、故辻井達一氏と私、白井隆が、共同で設立しました。 学術的に十勝海岸湖沼群と呼ばれる、大樹町の歴舟川から豊頃町の十勝川にはさまれた湖沼地帯は、ラムサール条約登録潜在候補地で、生物多様性に秀で、ランドスケープデザインに従事してきた私の目から見れば、実に風光明媚です。いまだに、公園法の網もかけられず、辻井氏いわく「民間主導で保全活動ができる、極めて稀な地域」です。 国際的なラムサール条約会議では、世界最先端の保全活動を、Wise Use、つまり、自然保護を必要とする産業の企画・経営事業として、模索、推進しています。辻井氏と私は、その挑戦をこの地域で進めようと考えたのです。 辻井達一氏は、北大教授を退官後、北海道環境財団の代表理事を16年間務めてきた、北海道の自然環境活動の第一人者でした。当初の4年間は辻井氏に代表理事を務めていただく約束で、私は、辻井氏の度量の大きな人柄を頼りに、生き生きと無邪気に新しい世界を泳ぎ回り、報告を書いたのです。ここに収めたものは、その中から選んだアーカイヴです。 しかし、湿原研究所設立後わずか10か月で、辻井氏は急逝されました。辻井氏の長く広く大きな経験世界を失い、私は自分自身をもって、環境世界の知見を得なければならなくなったのです。ぴたりと筆がとまりました。平成25年(2013年)1月15日のことでした。
自然観と教育① やまとごころ と てい 24.5.5
- 配信日
- 2017.10.01
- 記事カテゴリー:
- 第三巻 第一期湿原研究所ニュースレター・セレクション
大正時代に興った大正自由教育運動の流れの中に、中村春二(1877-1924)という人物がいます。東京都武蔵野の吉祥寺にある成蹊学園の創立者です。そう言うと特定の学校の枠の中で語ることに終始してしまいそうですが、それでは詰まらない。丸山真男が福沢諭吉に惚れて大部の論文を書いたように、この人物には学校の枠を超えて主題とするに値する教育観がある。特に、その教育指針の基礎にある『自然観』が興味深い。

それは、『やまとごころ』です。日本人の自然観を問われて、『しき島のやまとごころを人とわわば朝日に匂う山桜花』を思い浮かべる人は多いことでしょう。本居宣長はその心を「もののあわれ」と称したけれど、それは自然の森羅万象に感応する心、国学の原点です。中村春二は、46歳で早逝したために多くの著作を遺すことは叶いませんでしたが、教育者として「偉大な問い掛け」を遺しました。その『問い掛け』は『やまとごころ』に通ず。それを、手元にある資料を通して読み解き、明らかにしてみます。
ところで、一般社団法人湿原研究所と『やまとごころ』とどんな関係があるのか、と問う向きもあるやも知れませんが、それが大いにあるのです。この『自然観と教育』では、私達日本人の心の底に生きる自然について、解き明かしてみたいと思います。
参考にする資料は以下の6冊です。
教育論遺稿集「中村春二選集」
曽祖父で江戸文人として名高い説文学者山梨稲川の遺稿を、中村春二自身が編纂して明治四十五年に出版した「稲川遺芳」
父の国学者で歌人として名高い中村秋香の遺稿を、中村春二が編纂して明治四十四年に出版した「不盡迺屋遺稿(ふじのやいこう)」
教育の現場で仏教の経典のように生徒たちに読ませ暗記させた「心の力」小林一郎著
中村春二の次男中村浩(1910-1980微生物学者・理学博士)が書いた「人間中村春二伝」岩崎美術社刊
本人が書いたものは、「旅ころも」と「中村春二選集」。
二冊の遺稿集は、中村が教育者としての道を模索する途上、34歳で父中村秋香の遺稿集を編纂し、35歳で曽祖父山梨稲川の遺稿集を編纂、自らの出自を確認した仕事です。
資料を読み解くのは第二回以降の作業として、ここではまず、中村春二という教育者の足跡を整理してみます。
政治学者南原繁(1889-1974)は、中村春二についてこう評しました。
「わが国の近代教育史上、特筆すべき偉大な教育者が二人あると思います。その一人は吉田松陰。彼は御承知のごとく、幕末において、すでに広く世界を見わたし、封建制を打破して、明治維新の精神的基礎を築いたのであります。それは志士仁人―指導者の教育であり、その門下から維新の大業に参画した多くの逸材を輩出せしめた功績は大であります。
他の一人は中村春二先生。・・・先生の教育理念は、一言で申せば、指導者たる「英才」教育であるよりは、「人間」の教育-人間「個性」の育成であったと思います。・・・まさに人間の自由と文化的平和の世界を理想としたものということができましょう。だが、それはあくまで日本的土壌の上に培われ、愛国の至情に貫かれていたことは、松陰と相違はありません。また、・・・人間の魂と魂と触れ合う全人的教育方針と塾的形式を取ったことは、まさに現代教育の欠陥を突いて余りあります。」
南原繁がこの文を書いたのは1971年(昭和46年)ですから、ここで言う「現代教育」とはその頃を意味しています。
中国の浙江工商大学日本文化学院長王宝平教授は、文化大革命の時代に農村に下放され、山奥の村で教室を開いて子供たちに教育を施した頃のことを、夕食の席でしばしば語ります。『衣食足りて礼節を知る』という詞がありますが、人間はパンのみにて生くるに非ず、しかし、パンなくして教育はできない。若き王宝平教授は、礼節を知らぬ極貧の農民の姿にうちのめされ、数年ののちに都会に戻り、教育者の道を志したというのです。
政治と教育の葛藤は、簡単に言えば、パンと礼節の、卵と鶏論争みたいなものかも知れません。鄧小平まで国の指導者を務めた長征経験世代に続き、中国で現在50歳代を迎え国の舵取りを荷う世代は、この下放の体験を全身に叩き込んだ人々です。少なくとも現在の中国に、パンと礼節の確執は、鮮明に意識化されている。かつて、日本もそうでした。
江戸幕府は、寺子屋で論語を通して、為政者の礼節と哲学論を教え、国学の抬頭に対しては、朱子学、つまり忠君愛国を叩き込む学問の徹底で対抗しようとしました。一方で、吉田松陰が、明治維新を荷う若者たちに対して、心の拠り所、思想の基盤として教えたのが国学だと考えて良いかと思います。
明治時代には、富国強兵の掛け声に即して政府は教育に巨費を投じました。大正時代には日清日露の勝利と、第一次世界大戦の特需で湧く国民が、民主主義の訴えを大正デモクラシー運動として展開し、教育界もまた画一的な詰め込み教育に対する対案として、大正自由主義教育運動で答えました。
福沢諭吉、大隈重信が先陣を切った私学教育は、帝国大学中心の公教育に重きを置く政府からの弾圧を受けながらも、明治後期には地歩を築きましたが、後年大正自由教育運動と称された私学運動は、福沢、大隈に続く第二の波で、教育の画一化に突き進む政府の方針に対して、教育の自由を求めて独自の運動を展開し、日本女子大学、成蹊学園、自由学園、文化学院、明星学苑、玉川学園などに結実したことで知られます。
弱肉強食の外交に揉まれる政府は、国民の一枚岩となることを求め、人間の福祉向上を求める教育界は、人間の多様性尊重と品性の陶冶をこそ優先すべきであると訴える。
中村春二が生まれたのは明治10年(1877年)。国学を家業とする江戸文人の系譜に生まれ、国学者として世に出るつもりで、学業に精を出しました。江戸後期文人の元服の通過儀礼を踏襲して、18歳を過ぎるころから「枕頭山水」の境地を求め、山に入って放浪することを繰り返して自然への畏れを知り、尊き自然の中の人間存在に目覚めます。狩野派について習った絵を交えて、「旅ころも」という文集を自費出版したのもこの頃でした。
曽祖父の山梨稲川(とうせん)は明和八年庵原村で生まれ、のちに江戸に遊学し、文政元年駿府に居を定め、私塾を開き漢学を講じました。稲川は説文学者として名をなし、詩、文、書に長じて、数多くの漢詩をつくりました。稲川の詩は、遠く中国にまで知られ、清朝の碩儒として知られた有名な文人俞樾(1821-1907/愈曲園)は、稲川の詩集「稲川誌草」を評し『文藻富麗気韻高邁在東国詩人中当首座屈一指』、つまり稲川の詩はすばらしく、まさに日本の詩人中随一と評しました。明治十六年のことです。
また父中村秋香は、宮内省御歌所寄人を務めた歌人で、数多くの新体詩、和歌、評論等を残した高名な国学者でした。
中村春二は特にこの二人の先達を強く意識して育ちましたが、のちに代々国学者であった家職を投げ打ち、教育界に身を投じたのです。
はじめは、中流以下の家庭の子弟を対象とした私塾の形から始めました。これは当時の社会情勢下では義務教育による小学卒業のみでは自立自活の力が与えられず、さりとて中等教育を受けるには少なからぬ学資を必要とするため、恵まれない境遇の子弟に対し、進学の途をひらくことを目的としました。大衆のなかに埋もれている未来のエリート解放、人材発掘を目指したのです。その後、竹馬の友である三菱の岩崎小弥太と、銀行家今村繁三から物心両面の援助を受けて、学校設立へと向かいますが、中村春二は、自分は教育には素人であると常々その著述を通して語っています。それは、初めから教科書にすべき教育論などを持たず、実践を通して手さぐりで教育論を築いたことを意味しています。
まず中村春二は、政府が推し進める画一化教育を、生産社会に適応する人材養成に過ぎないと批判しました。教育とは本来、時局の変動から遊離し、時の政府の政策に利用されることなく、また思想界の変動によって左右されることなく、人間自身の人格の教育であるべきものである。そこには教育の永遠性がなければならない。詰め込みに終始して、子供に受け身の教育を押し付ける国の在り方に疑問を呈し、義務教育を廃止せよとまで訴えました。教育とは、自発的な意思による、自己教育以外にはない。人格教育こそが、教育の本質だと考えたのです。
また、時代はヒューマニズムを訴えていました。中村春二も、ヒューマニズムによる人間観は尊重しましたが、人間の教育はあくまで日本的土壌の上に培い、愛国の至情をもって、これを貫くべきであると考えたのです。日本的土壌の上に立っての精神主義に立脚するものでなければならないと。中村春二的教育にみられる思想的性格は、自ずから西欧的近代教育思潮とは異なるものでした。時代を席巻していたジョン・デューイの自由主義教育、エレン・ケイの児童中心主義教育、リーツの田園教育等の影響は受けましたが、中村春二は決してこれの模倣はしなかった。春二はむしろこうした欧米流の教育謳歌の風潮に対して抵抗し、欧米から流入した個人主義を排撃しました。
同時に中村春二は、日本に深く浸透している中国文化の排撃すら考えました。特に、国語から漢字を駆逐せよと主張しました。漢字の混入が、「やまとごころ」を語る日本語を混乱に陥れている。漢文はあくまでも外国語として学習すべきものであって、「やまとごころ」は、ひらがなで表すべきものだというのです。
それでは、中村春二は教育の目的を何に置いたのか。
西欧的近代教育思潮において近代教育は、個人の自我の開発による中世的人間像からの解放であり、封建的、儒教的人間からの脱却でしたが、彼は西欧的な精神主義軽視を否定し、むしろ苦行的精神主義を重視しました。つまり自らの『悟り』なくして真の解放はない。
中村春二は、自我中心主義を疑ったのです。自我に代わるものとして、『真我』を開発する、と言いました。真我とは、人間の心の奥に潜んでいる、人間存在に共通する「善」とでも言いましょうか。あるいは善を越えた自然の摂理。国学者が見極めようとした、人間を含む自然的世界の奥義が、そこに存在します。
それは中村春二の国家観にも通じます。国家は家族の拡大されたものであると解釈し、『上下心ヲ一ニスル』基盤を家族主義に求めて、家長である天皇の意義を認めていました。したがって、当然のことながら個人主義を排撃し、自我は単に個人の自我ではなく、他人との関係をも含んだ社会的自我でなければならないと説いたのです。
中村春二は実践法として、曹洞宗の僧堂教育にその拠りどころを見出しました。教育の標語を、『個性の尊重』、『品性の陶冶』、『勤労の実践』として、精神統一法としての凝念法と心力歌の唱和、不言実行の作業教育、品性陶冶の方法としての同朋同行の教育、鍛錬教育としての夏期冬期の諸行事等々、いずれも人格教育のための独自な徹底した教育方法を実行したのです。また、労働を蔑視する気風を是正すべきであるとして、学校の重要行事として労働作業を課しました。凝念に象徴される精神修養、気力の養成などの克己主義、断食、徹夜会、寒中水泳等々の多彩な鍛錬主義教育が徹底的に実施されたのです。
その教育論は、型にはまった『正統派』の教育に対し、『異端』として受けとられましたが、このことが却って幸いし、その反骨精神と実践力と相俟って、存分にその独創性を発揮できたものと考えられます。高踏的ともいうべき伝統的な人格教育です。それは大変な評判を呼んで、毎日多くの見学者が押し掛け、教育に熱心な高学歴層つまり富裕層がこぞって、子弟の教育を依頼するようになりました。
中村春二という人物は、客観的にみて浪漫派ともいえる純粋無垢な教育者でした。教育の永遠性を信じ、無我夢中に働いたのですが、激務が祟って命を縮めてしまいました。その結果、私達は中村春二があと30年の時間を生きていたら到達していたであろう教育観を見聞きすることはできません。
しかし、中村春二が目指した真我の開発、そして、自我の開発に基づく近代合理主義に対する批評的姿勢は、今もなお深く評価すべき問い掛けであると思われます。なぜなら、生態学を拠りどころとして現代の心ある人々が追い求めている自然思想の到達点に、どうやら、中村春二が真我と称した、自然的世界の本質に対する共通の理解、分析的な自然科学や機械的人間思想に基礎を置く土木建築工学、はたまた機能と効率を追い続ける情報工学を越えた、世界に対する文人的な言説が見えているからです。
ロングトレイル、フットパス、エコビレッジ、ワイズユース、エクスカーション・・・・我が国の環境世界を席巻するカタカナ言葉になじめない人々もまた、自然的世界との長く楽しい遊興を願うのであればこそ、中村春二の思想的苦闘を沈思して、今にふさわしい「問い」を見出すことに意味があります。
その手掛かりは、「体」と言うべきものであろうと思われます。風体、体たらくと呼ぶときに使う「てい」。
仏の文人フローベールが「文体がすべてだ」と語った「体」。
茶道で言う「このみ」。
自然的世界と人間の長く楽しい繁栄を願う者みなが追い求める、世界の在り様。その表れとしての「てい」。
フェノロサと岡倉天心が「とるに足らぬ」と文人画を日本美術史から捨てた、その時代風潮に対して抗議する中村春二の体。
本居宣長は、その体に「もののあわれ」を見出したのだと考えれば、中村春二というもがき格闘した体について、もう少し考えてみる値打ちはありそうだと思います。

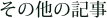 [第三巻 第一期湿原研究所ニュースレター・セレクション]
[第三巻 第一期湿原研究所ニュースレター・セレクション]